

地主さん向けコラム
遺言書を作るときに必ず入れるべき3項目とは? ~地主こそ準備が必要な“争族”対策の核心~
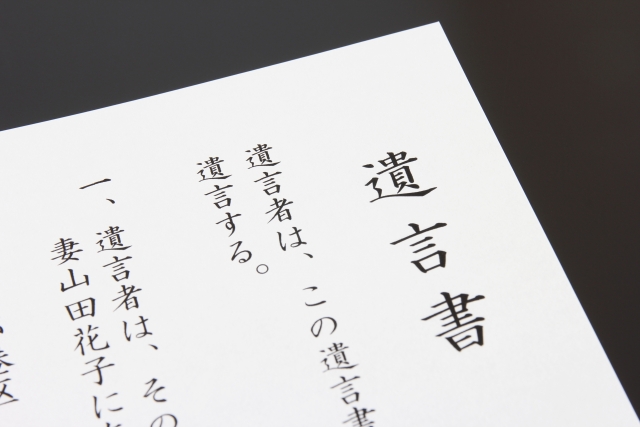
土地や建物を複数所有している地主にとって、相続は避けて通れない現実です。
しかし、「うちは家族仲がいいから大丈夫」「長男に継がせるつもりだから遺言なんて必要ない」と思っていませんか?
実際に、**地主の相続で最も多いトラブル原因は“遺言書がなかったこと”**です。
どれだけ家族の中で話し合いができていたとしても、法的な根拠がないと、後から揉める火種になります。
特に地主は、不動産という分けにくい財産を多く持っているため、
現金のように単純に“割る”ことができず、遺産分割が非常に難航しやすいのです。
この記事では、地主が遺言書を作成する際に「必ず入れるべき3項目」を、
実際の相続実務や紛争事例を踏まえながら、3部構成で解説します。
第1部:「誰に何を相続させるか」を明確に記載
◆分けにくい土地こそ指定すべき
地主が所有する財産の多くは、土地・建物といった不動産資産です。
不動産は現金のように平等に分けることが難しく、遺言書で明確に指定しないと、
「この土地は誰がもらうのか」
「建物と土地を別の人が相続してよいのか」
「収益不動産の家賃は誰のものか」
といった点があいまいになり、兄弟姉妹間で争いになります。
したがって、遺言書には必ず、
「○○市□□町の土地(地番●番●)は長男Aに相続させる」
「△△ビル(建物登記簿番号●●)は次男Bに相続させる」
というように、対象不動産と受け取り人をセットで明記する必要があります。
◆法定相続分では解決できない地主の事情
仮に遺言書がなかった場合、民法の定める「法定相続分」に従って、相続人で遺産を分けることになります。
たとえば、妻1/2、子2人が1/4ずつ、という具合です。
しかし、地主のように「一つの土地にアパートが建っている」「収益性のある貸地がある」場合、
不動産を分けて所有することは現実的に運用リスクを高めてしまいます。
・一つの土地を2人で共有 → 売却・建替えに同意が必要
・アパートの収入を複数人で分ける → 経費負担の分担が揉める
・管理責任が不明確になり放置 → 賃貸トラブルへ発展
このような状態を避けるためにも、地主の遺言書では「この土地はこの人」と割り切って明記することが非常に重要です。
地主が所有する財産の多くは、土地・建物といった不動産資産です。
不動産は現金のように平等に分けることが難しく、遺言書で明確に指定しないと、
「この土地は誰がもらうのか」
「建物と土地を別の人が相続してよいのか」
「収益不動産の家賃は誰のものか」
といった点があいまいになり、兄弟姉妹間で争いになります。
したがって、遺言書には必ず、
「○○市□□町の土地(地番●番●)は長男Aに相続させる」
「△△ビル(建物登記簿番号●●)は次男Bに相続させる」
というように、対象不動産と受け取り人をセットで明記する必要があります。
◆法定相続分では解決できない地主の事情
仮に遺言書がなかった場合、民法の定める「法定相続分」に従って、相続人で遺産を分けることになります。
たとえば、妻1/2、子2人が1/4ずつ、という具合です。
しかし、地主のように「一つの土地にアパートが建っている」「収益性のある貸地がある」場合、
不動産を分けて所有することは現実的に運用リスクを高めてしまいます。
・一つの土地を2人で共有 → 売却・建替えに同意が必要
・アパートの収入を複数人で分ける → 経費負担の分担が揉める
・管理責任が不明確になり放置 → 賃貸トラブルへ発展
このような状態を避けるためにも、地主の遺言書では「この土地はこの人」と割り切って明記することが非常に重要です。
第2部:「付言事項」で想いと背景を記す
◆遺言に“感情”と“理由”を添える効果
遺言書の中には「法的効力を持たないが、意思として伝える」部分があり、これを付言事項(ふげんじこう)といいます。
たとえば、
「長男に土地を相続させるのは、今後の管理責任を考えてのことです」
「次男には現金を多く残しましたが、日頃の介護への感謝からです」
「不動産の共有を避けるため、このように分けました」
といった一文を添えるだけで、他の相続人の納得度が高まるケースは非常に多いのです。
地主が不動産を偏った形で誰かに相続させる場合、“なぜこの人に残したのか”という説明があるかないかで、トラブル発生率は大きく変わります。
◆「争族」を防ぐのは“法”と“心”の両輪
遺言書は、あくまで法律文書です。しかし、相続という場面では心の納得も大切です。
特に地主の家庭では、
・長男が不動産を継いだ
・次男は都市部で自分の家を持っている
・長女は介護していたのに不動産をもらえなかった
というように、「公平性」と「平等性」が衝突しやすくなります。
付言事項を活用することで、地主の想いを後世に伝えることができ、相続人の感情的な衝突を緩和できます。
遺言書の中には「法的効力を持たないが、意思として伝える」部分があり、これを付言事項(ふげんじこう)といいます。
たとえば、
「長男に土地を相続させるのは、今後の管理責任を考えてのことです」
「次男には現金を多く残しましたが、日頃の介護への感謝からです」
「不動産の共有を避けるため、このように分けました」
といった一文を添えるだけで、他の相続人の納得度が高まるケースは非常に多いのです。
地主が不動産を偏った形で誰かに相続させる場合、“なぜこの人に残したのか”という説明があるかないかで、トラブル発生率は大きく変わります。
◆「争族」を防ぐのは“法”と“心”の両輪
遺言書は、あくまで法律文書です。しかし、相続という場面では心の納得も大切です。
特に地主の家庭では、
・長男が不動産を継いだ
・次男は都市部で自分の家を持っている
・長女は介護していたのに不動産をもらえなかった
というように、「公平性」と「平等性」が衝突しやすくなります。
付言事項を活用することで、地主の想いを後世に伝えることができ、相続人の感情的な衝突を緩和できます。
第3部:「遺言執行者の指定」で実行力を担保する
◆執行者がいないと、遺言が“絵に描いた餅”になる
せっかく遺言書を残しても、それを実際に実行する人がいないと、
相続人同士で「どうするの?」と揉めてしまい、遺言の内容が守られないリスクがあります。
そこで、遺言書の中で「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を明記しておくことが極めて重要です。
遺言執行者には、
・指定された相続人
・第三者の司法書士・弁護士
・信頼できる不動産コンサルタントや行政書士
などを指名できます。
特に地主のように「相続財産の大半が不動産」の場合は、法務局での登記変更・名義変更など専門的な手続きが不可欠なので、専門家に任せるケースが増えています。
◆実務では「執行者が誰か」が揉める
遺言書に執行者の記載がなかった場合、
・相続人同士が執行者を巡って争う
・一部の相続人が非協力的になる
・名義変更や預金解約が進まない
といったトラブルが発生します。
地主のように大きな資産を持つ場合は、相続が“プロジェクト”になることもあります。
そのため、「執行責任者=舵取り役」が必要不可欠なのです。
せっかく遺言書を残しても、それを実際に実行する人がいないと、
相続人同士で「どうするの?」と揉めてしまい、遺言の内容が守られないリスクがあります。
そこで、遺言書の中で「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を明記しておくことが極めて重要です。
遺言執行者には、
・指定された相続人
・第三者の司法書士・弁護士
・信頼できる不動産コンサルタントや行政書士
などを指名できます。
特に地主のように「相続財産の大半が不動産」の場合は、法務局での登記変更・名義変更など専門的な手続きが不可欠なので、専門家に任せるケースが増えています。
◆実務では「執行者が誰か」が揉める
遺言書に執行者の記載がなかった場合、
・相続人同士が執行者を巡って争う
・一部の相続人が非協力的になる
・名義変更や預金解約が進まない
といったトラブルが発生します。
地主のように大きな資産を持つ場合は、相続が“プロジェクト”になることもあります。
そのため、「執行責任者=舵取り役」が必要不可欠なのです。
地主にとって、遺言書は争いを防ぎ、大切な不動産を正しく引き継がせるための“最強のツール”です。
遺言書には、次の3つを必ず入れましょう:
1. 「誰に、どの不動産を相続させるか」を明記
→ 地番・建物の登記番号を具体的に書くことがカギ
2. 「付言事項」で想いや理由を記す
→ なぜその人に遺すのか、他の相続人へのメッセージも添えて
3. 「遺言執行者」の指定
→ 登記や手続きを確実に実行してくれる人・専門家を選任
地主が築いた財産を、スムーズかつ円満に次世代へつなぐためには、
生前からの備えと、“想い”を込めた遺言書の作成が欠かせません。
「いつかやろう」と思っているうちに、その「いつか」は突然やってきます。
地主である今、未来のトラブルを防ぐための一歩を踏み出してみませんか?
遺言書には、次の3つを必ず入れましょう:
1. 「誰に、どの不動産を相続させるか」を明記
→ 地番・建物の登記番号を具体的に書くことがカギ
2. 「付言事項」で想いや理由を記す
→ なぜその人に遺すのか、他の相続人へのメッセージも添えて
3. 「遺言執行者」の指定
→ 登記や手続きを確実に実行してくれる人・専門家を選任
地主が築いた財産を、スムーズかつ円満に次世代へつなぐためには、
生前からの備えと、“想い”を込めた遺言書の作成が欠かせません。
「いつかやろう」と思っているうちに、その「いつか」は突然やってきます。
地主である今、未来のトラブルを防ぐための一歩を踏み出してみませんか?


