

地主さん向けコラム
遺言書を作るときに必ず入れるべき3項目
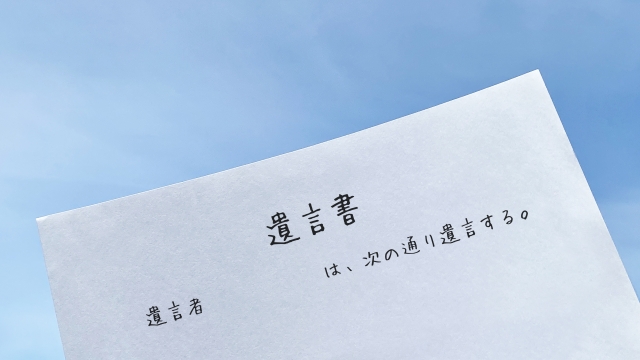
地主にとって、自分が築いてきた不動産や金融資産を次世代にスムーズに承継させることは大きな責任です。相続トラブルを未然に防ぎ、家族に迷惑をかけないためには、遺言書の作成が欠かせません。特に、地主は不動産という「分けにくい資産」を多く所有しているため、遺言書がない場合、相続人同士の争いが長期化しやすくなります。
しかし、ただ遺言書を作れば安心というわけではありません。内容に抜けや曖昧さがあれば、かえって相続トラブルの火種になりかねません。そこで今回は、地主が遺言書を作るときに必ず入れておくべき3つの項目を、税務や法律の観点も踏まえて詳しく解説します。
第1部:地主が遺言書で必ず明記すべき「財産の特定」
地主にとって、遺言書の最も重要な要素は「どの財産を誰に渡すのか」を明確にすることです。特に地主が所有する土地や建物は、評価額が高く、共有にするとトラブルが起きやすいため、相続人間で揉めないよう正確な特定が不可欠です。
◆不動産の記載方法
単に「自宅を長男に相続させる」と書くだけでは不十分です。不動産の場合は、登記簿上の所在地、地番、家屋番号などを正確に記載します。
たとえば、
「東京都世田谷区○○1丁目2番3 宅地 200㎡」
「東京都世田谷区○○1丁目2番3 家屋番号1234 木造2階建」
といった具合に、登記事項証明書に基づいた表記が必要です。
◆預貯金や有価証券の場合
銀行名、支店名、口座番号、銘柄や口数まで特定します。地主は不動産以外にも金融資産を複数の銀行や証券会社に分散していることが多く、これらを漏れなく書くことで、相続人がスムーズに手続きを行えます。
◆財産特定が重要な理由
財産の特定が不十分だと、相続人が「この土地は遺言書に含まれるのか」「この口座は誰のものか」と争う原因になります。地主の場合、不動産の筆数が多くなりやすいため、特定は慎重に行う必要があります。
◆不動産の記載方法
単に「自宅を長男に相続させる」と書くだけでは不十分です。不動産の場合は、登記簿上の所在地、地番、家屋番号などを正確に記載します。
たとえば、
「東京都世田谷区○○1丁目2番3 宅地 200㎡」
「東京都世田谷区○○1丁目2番3 家屋番号1234 木造2階建」
といった具合に、登記事項証明書に基づいた表記が必要です。
◆預貯金や有価証券の場合
銀行名、支店名、口座番号、銘柄や口数まで特定します。地主は不動産以外にも金融資産を複数の銀行や証券会社に分散していることが多く、これらを漏れなく書くことで、相続人がスムーズに手続きを行えます。
◆財産特定が重要な理由
財産の特定が不十分だと、相続人が「この土地は遺言書に含まれるのか」「この口座は誰のものか」と争う原因になります。地主の場合、不動産の筆数が多くなりやすいため、特定は慎重に行う必要があります。
第2部:地主が必ず決めるべき「分配方法と受け継ぐ理由」
財産の特定に加えて、どの財産を誰に渡すのかという分配方法を明確にし、その理由を簡潔に記すことも、地主にとっては重要なポイントです。
◆分配の具体例
「自宅土地建物は長男に相続させる」
「賃貸アパートAは次男に相続させる」
「現金2,000万円は長女に相続させる」
地主の場合、賃貸物件や農地など収益を生む資産を持つことが多いため、分配時には相続人間の公平性に配慮が必要です。たとえば、アパートを相続する子は将来の家賃収入を得られる一方で、現金を受け取る子はその後の収入がありません。このような格差が争いの原因になることがあります。
◆分配理由の記載
法律的には理由を書かなくても遺言書は有効ですが、理由があると相続人が納得しやすくなります。
例:
「長男は私と同居し、地主としての土地管理を長年手伝ってきたため、自宅と隣接する土地を相続させる」
「次男は賃貸アパートの運営に関わってきたため、アパートを相続させる」
理由を添えることで、相続人同士の理解が得やすくなり、遺言書の効果が高まります。
◆分配の具体例
「自宅土地建物は長男に相続させる」
「賃貸アパートAは次男に相続させる」
「現金2,000万円は長女に相続させる」
地主の場合、賃貸物件や農地など収益を生む資産を持つことが多いため、分配時には相続人間の公平性に配慮が必要です。たとえば、アパートを相続する子は将来の家賃収入を得られる一方で、現金を受け取る子はその後の収入がありません。このような格差が争いの原因になることがあります。
◆分配理由の記載
法律的には理由を書かなくても遺言書は有効ですが、理由があると相続人が納得しやすくなります。
例:
「長男は私と同居し、地主としての土地管理を長年手伝ってきたため、自宅と隣接する土地を相続させる」
「次男は賃貸アパートの運営に関わってきたため、アパートを相続させる」
理由を添えることで、相続人同士の理解が得やすくなり、遺言書の効果が高まります。
第3部:地主が忘れてはならない「遺言執行者の指定」
遺言書の内容を実際に執行する役割を担うのが遺言執行者です。地主の場合、不動産の名義変更や賃貸契約の引き継ぎ、農地の権利移転など、相続に伴う事務作業は非常に複雑になります。
◆遺言執行者を指定するメリット
・不動産登記や金融機関手続きを一括で進められる
・相続人同士の連絡調整を遺言執行者が担うため、感情的対立を避けられる
・専門家を選べば、地主特有の税務・法務の問題にも対応可能
遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますが、地主の場合は弁護士や司法書士などの専門家を選ぶ方が無難です。
◆遺言執行者の選び方
・不動産や農地の相続経験が豊富
・税務署や法務局とのやり取りに慣れている
・信頼でき、かつ中立的な立場を保てる人物
遺言執行者を指定しないと、相続人全員の合意で手続きを進める必要があり、不動産が多い地主の場合は手続きが長期化するリスクがあります。
◆遺言執行者を指定するメリット
・不動産登記や金融機関手続きを一括で進められる
・相続人同士の連絡調整を遺言執行者が担うため、感情的対立を避けられる
・専門家を選べば、地主特有の税務・法務の問題にも対応可能
遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますが、地主の場合は弁護士や司法書士などの専門家を選ぶ方が無難です。
◆遺言執行者の選び方
・不動産や農地の相続経験が豊富
・税務署や法務局とのやり取りに慣れている
・信頼でき、かつ中立的な立場を保てる人物
遺言執行者を指定しないと、相続人全員の合意で手続きを進める必要があり、不動産が多い地主の場合は手続きが長期化するリスクがあります。
地主が遺言書を作るときに必ず入れるべき3項目は、
1.財産の特定
2.分配方法と理由
3.遺言執行者の指定
これらを明確に記載することで、相続人間の争いを防ぎ、地主として築いた資産を円滑に次世代へ引き継ぐことができます。特に地主は、不動産や農地など分けにくい資産を多く持つため、遺言書の精度が相続の成否を左右します。
遺言書は「書くこと」よりも「正しく書くこと」が重要です。地主としての責任を果たすためにも、専門家の助言を受けながら、家族の将来を見据えた遺言書を用意しておきましょう。
1.財産の特定
2.分配方法と理由
3.遺言執行者の指定
これらを明確に記載することで、相続人間の争いを防ぎ、地主として築いた資産を円滑に次世代へ引き継ぐことができます。特に地主は、不動産や農地など分けにくい資産を多く持つため、遺言書の精度が相続の成否を左右します。
遺言書は「書くこと」よりも「正しく書くこと」が重要です。地主としての責任を果たすためにも、専門家の助言を受けながら、家族の将来を見据えた遺言書を用意しておきましょう。


