

地主さん向けコラム
サブリース契約と地主リスク ~安定収入の裏に潜む落とし穴~
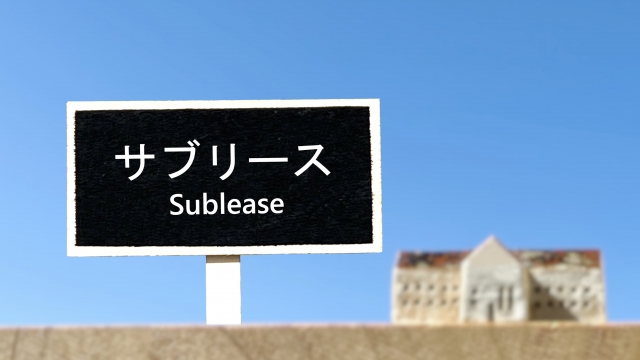
不動産を所有する地主のもとには、ハウスメーカーや管理会社からよくこういった提案が舞い込みます。
「空室の心配ゼロ!」「毎月固定の家賃を保証!」「将来も安定した資産運用ができますよ!」
それが“サブリース契約”と呼ばれる仕組みです。
アパートやマンションを建てると同時に、建築会社や管理会社が借り上げ、地主に一定額の賃料を支払うというもの。
たしかに一見すると、地主にとっては安心で手間もなく、ありがたい提案のように思えるかもしれません。
しかし、近年このサブリース契約を巡って多くのトラブルが報告されているのも事実。
本記事では、サブリース契約の仕組みを改めて整理しながら、地主が注意すべきポイントと対策について解説します。
第1部:そもそも「サブリース契約」とは?地主にとってのメリットとカラクリ
◆サブリースの基本構造
サブリース契約とは、建物完成後に不動産会社(サブリース業者)が一括で物件を借り上げ、
さらに第三者(入居者)に転貸(また貸し)するスキームです。
地主との間に結ばれる契約は「転貸を前提とした賃貸借契約」。
このため、入居者の有無にかかわらず、毎月の賃料は保証されます。
◆地主にとってのメリット
・空室リスクを負わずに毎月一定収入を得られる
・入居者募集・管理業務が不要(完全お任せ)
・建築とサブリースがセットで提案されることが多く、初期設計がラク
特に地主が高齢の場合や、相続対策としての土地活用を検討している場合に、
「手間がかからない」「収入が安定している」という点は大きな魅力となります。
◆しかし、そこに“カラクリ”がある
サブリース契約は、必ずしも「契約どおりにずっと収入が保証される」わけではありません。
実は多くの契約には、
・賃料の見直し(減額)条項
・中途解約条項(更新時など)
が含まれており、地主が一方的に不利益を被ることも。
このように、地主がサブリース契約を「完全保証型」だと誤解してしまうことで、将来的なトラブルへとつながってしまうのです。
サブリース契約とは、建物完成後に不動産会社(サブリース業者)が一括で物件を借り上げ、
さらに第三者(入居者)に転貸(また貸し)するスキームです。
地主との間に結ばれる契約は「転貸を前提とした賃貸借契約」。
このため、入居者の有無にかかわらず、毎月の賃料は保証されます。
◆地主にとってのメリット
・空室リスクを負わずに毎月一定収入を得られる
・入居者募集・管理業務が不要(完全お任せ)
・建築とサブリースがセットで提案されることが多く、初期設計がラク
特に地主が高齢の場合や、相続対策としての土地活用を検討している場合に、
「手間がかからない」「収入が安定している」という点は大きな魅力となります。
◆しかし、そこに“カラクリ”がある
サブリース契約は、必ずしも「契約どおりにずっと収入が保証される」わけではありません。
実は多くの契約には、
・賃料の見直し(減額)条項
・中途解約条項(更新時など)
が含まれており、地主が一方的に不利益を被ることも。
このように、地主がサブリース契約を「完全保証型」だと誤解してしまうことで、将来的なトラブルへとつながってしまうのです。
第2部:実際にあった地主のサブリーストラブルとリスク
◆ケース1:家賃10年固定と言われたのに、5年で減額通知
ある地主が建てたアパートは、月60万円で借り上げるという契約でサブリースがスタート。
「これなら借入返済も楽勝だ」と安心していたところ、5年目に突如「家賃50万円へ減額」と通告。
契約書を見ると、「5年ごとの家賃見直し条項」が明記されていた。
地主は「営業時に説明されなかった!」と憤ったが、書面にはサイン済みで反論は通らず。
→ ポイント:営業トークではなく契約書の条文で判断すべし
◆ケース2:空室が多くなり、サブリース会社が撤退
別の地主は、建物を建てて数年間は順調に収入を得ていた。
しかし、周辺に新築アパートが乱立し、入居率が低下。
「これ以上の借り上げはできない」とサブリース会社から契約解除を申し出される。
自力で入居者募集・管理を行う術もなく、結果として収益は大幅にダウン。
→ ポイント:市場動向によってサブリース契約は継続されない可能性あり
◆ケース3:借上家賃が市場より安すぎる
サブリース契約時に提示された家賃が、実勢よりかなり低かった例も。
実際にはもっと高く貸せる地域なのに、「保証」と引き換えに低水準で固定されていた。
地主は長期にわたって“損をしていた”ことに後で気づくも、時すでに遅し。
→ ポイント:保証の代償は「収益性の低さ」。適正賃料か必ず確認を
ある地主が建てたアパートは、月60万円で借り上げるという契約でサブリースがスタート。
「これなら借入返済も楽勝だ」と安心していたところ、5年目に突如「家賃50万円へ減額」と通告。
契約書を見ると、「5年ごとの家賃見直し条項」が明記されていた。
地主は「営業時に説明されなかった!」と憤ったが、書面にはサイン済みで反論は通らず。
→ ポイント:営業トークではなく契約書の条文で判断すべし
◆ケース2:空室が多くなり、サブリース会社が撤退
別の地主は、建物を建てて数年間は順調に収入を得ていた。
しかし、周辺に新築アパートが乱立し、入居率が低下。
「これ以上の借り上げはできない」とサブリース会社から契約解除を申し出される。
自力で入居者募集・管理を行う術もなく、結果として収益は大幅にダウン。
→ ポイント:市場動向によってサブリース契約は継続されない可能性あり
◆ケース3:借上家賃が市場より安すぎる
サブリース契約時に提示された家賃が、実勢よりかなり低かった例も。
実際にはもっと高く貸せる地域なのに、「保証」と引き換えに低水準で固定されていた。
地主は長期にわたって“損をしていた”ことに後で気づくも、時すでに遅し。
→ ポイント:保証の代償は「収益性の低さ」。適正賃料か必ず確認を
第3部:地主がサブリース契約で後悔しないための対策
① 契約前の「リスク説明」を受けること
不動産会社や管理会社の提案を受けた際は、以下を必ず確認しましょう。
・家賃減額条項はどのタイミングで発動されるか
・借上契約は何年単位で更新か(自動更新か)
・中途解約の条件と、地主に不利な項目があるか
・借上賃料が相場と比べて妥当か
地主としては、“いいことばかり”しか説明しない営業トークに惑わされず、
契約書を専門家に見せる冷静さが重要です。
② 地主自身が“出口戦略”を考える
「将来この土地はどう使いたいか」「何年持ちたいか」など、地主としての経営戦略をもつことが不可欠です。
・短期的にはサブリースが安心でも、
・売却したい
・自分で貸したい
・子どもに引き継ぎたい
という将来像があるなら、そのタイミングと契約内容の整合性が必要。
地主として、目先の収益だけでなく、“どう終わらせるか”までを見据えた契約を心がけましょう。
③ 困ったらすぐに相談を!
・不当な減額通告を受けた
・契約内容に納得がいかない
・契約解除を打診された
こうしたとき、地主は一人で抱え込まず、
弁護士や不動産コンサルタント、税理士など専門家のサポートを受けることが肝心です。
「地主であるあなたの立場を守る第三者」を持つことが、冷静な対応に繋がります。
不動産会社や管理会社の提案を受けた際は、以下を必ず確認しましょう。
・家賃減額条項はどのタイミングで発動されるか
・借上契約は何年単位で更新か(自動更新か)
・中途解約の条件と、地主に不利な項目があるか
・借上賃料が相場と比べて妥当か
地主としては、“いいことばかり”しか説明しない営業トークに惑わされず、
契約書を専門家に見せる冷静さが重要です。
② 地主自身が“出口戦略”を考える
「将来この土地はどう使いたいか」「何年持ちたいか」など、地主としての経営戦略をもつことが不可欠です。
・短期的にはサブリースが安心でも、
・売却したい
・自分で貸したい
・子どもに引き継ぎたい
という将来像があるなら、そのタイミングと契約内容の整合性が必要。
地主として、目先の収益だけでなく、“どう終わらせるか”までを見据えた契約を心がけましょう。
③ 困ったらすぐに相談を!
・不当な減額通告を受けた
・契約内容に納得がいかない
・契約解除を打診された
こうしたとき、地主は一人で抱え込まず、
弁護士や不動産コンサルタント、税理士など専門家のサポートを受けることが肝心です。
「地主であるあなたの立場を守る第三者」を持つことが、冷静な対応に繋がります。
サブリース契約は、たしかに地主にとって便利な仕組みです。
ただし、その“便利さ”の裏側には以下のようなリスクが潜んでいます。
◆ 地主が知るべきサブリースの真実
・保証家賃は「永続」ではなく、「見直し」前提
・契約内容次第で、地主は不利な立場にもなる
・市場悪化で業者が撤退すれば、地主がすべて背負うことに
・借上賃料が適正か、契約書の読み込みが不可欠
地主がサブリースを活用するなら、
契約の仕組みと将来リスクを正しく理解し、納得の上で進めることが大前提です。
「楽に稼げる」「空室ゼロ」といった甘い言葉に乗るのではなく、
地主として経営者目線をもって、“判断と責任”を明確にすること。
それが、サブリース契約との上手な付き合い方なのです。
ただし、その“便利さ”の裏側には以下のようなリスクが潜んでいます。
◆ 地主が知るべきサブリースの真実
・保証家賃は「永続」ではなく、「見直し」前提
・契約内容次第で、地主は不利な立場にもなる
・市場悪化で業者が撤退すれば、地主がすべて背負うことに
・借上賃料が適正か、契約書の読み込みが不可欠
地主がサブリースを活用するなら、
契約の仕組みと将来リスクを正しく理解し、納得の上で進めることが大前提です。
「楽に稼げる」「空室ゼロ」といった甘い言葉に乗るのではなく、
地主として経営者目線をもって、“判断と責任”を明確にすること。
それが、サブリース契約との上手な付き合い方なのです。


